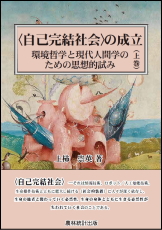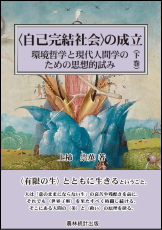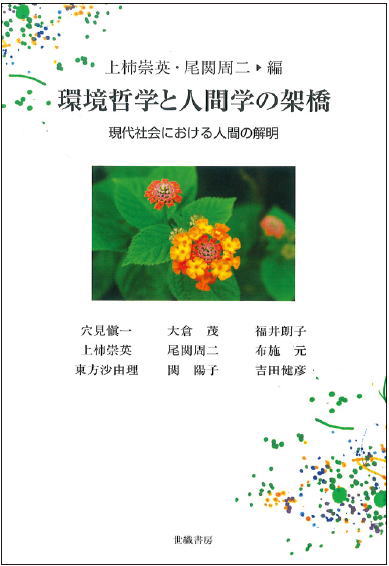以前「持続可能性は何を持続させるのか?」という記事を書かせていただいたAndTechさん刊行の『環境配慮材料』に、新しい記事を書かせていただきました。
上柿崇英(2025a)「「天空城」はどこへ?――環境問題の起源と「社会環境」の人類史」『環境配慮型材料』、AndTech、 vol.12、pp.95-109
やや奇妙なタイトルかもしれませんが、この記事では、これまで筆者が論じてきた環境哲学の枠組みを土台として、私たちが生きる現代社会の抱えている持続不可能性の問題を、「天空城」の比喩というものを用いて論じています。
ここで、空高く浮遊する巨大な城のことを想像してみてください。その「天空城」は、周囲を城壁で取り囲まれ、城壁の内側には、整備された農地や庭園とともに、大勢の人間たちが暮らしています――。
私たち人間は、実は自然生態系=「自然環境」のうえに人工的な環境=「社会環境」をつくりだし、しかもそれを、世代を越えて膨張/蓄積させていくという特殊な性質を備えた存在です。
人間が創出した「社会環境」は、やがて長い年月の末に巨大な人工物の集積物として発展していきますが、重要なことは、それが化石燃料の使用をひとつのきっかけとして、土台となっていたはずの「自然環境」から分離し、科学技術を用いて、加速度的に膨張/蓄積していくシステムへと変貌していったということです。
本論ではその様子を、かつて大地に根ざしていたはずの都市が、大地から浮遊した「天空城」へと変貌していく姿として比喩的に論じているわけです。

気候変動を含む多くの問題を抱えた私たちは、言ってみれば浮遊状態に限界を感じながらも、なんとかして現状維持を図ろうとしている「天空城」とよく似た状態にあります。
そして最も確実な問題解決の方法は、「天空城」を大地へと帰還させることとなるのですが、私たちはその選択をできそうにもありません。
というのも、SDGsにも体現された、現代の人間的な理想が求める、80億人が富裕国並みの物質的・社会的水準を達成するという方向性は、大地への帰還とは逆の方向性であること、そして大地への帰還を果たすためには、人々には等身大の「助け合い」が求められるものの、すでに私たちは便利で快適で、自己決定が保障された生活に慣れすぎてしまっており、いまさら「助け合い」で生活していける自信も、スキルもないと感じているからです
(この問題について関心のある方は、以下の解説記事をご参照ください)。
大地への帰還ができそうにもなく、浮遊状態のを何とか延命させようともがき、最後は、なし崩し的に科学技術による強行突破という賭けに打って出ようとしている――それが本論で描きだされる私たちの姿です。
その”賭け”がもたらす人間の未来を、本論では思考実験的に、「「天空城」の要塞化」、「惑星の「天空城」化」という形で描きました。そのいずれかが成功すれば、理論的には環境問題そのものが”撲滅”されることとなるでしょう。
しかし科学技術がそのような未来を約束してくれる保障などまったくありません。その意味において、その”賭け”は依然として、大きなリスクを伴う賭けであると言えるでしょう。
なお、本論では明記していませんが、実は本論は、宮崎駿監督による『天空の城ラピュタ』(スタジオジブリ、1986)を意識して書かれたものでもあります。
作中の「ラピュタ王国」は、科学技術の力によって「天空城」を築きあげ、強大な軍事力によって地上を支配し、繁栄したとされています。しかしオープニングでは、原因は明かされないながらも、「ラピュタ王国」が滅び、人々が大地へと還っていく姿が描かれています。
登場人物であるムスカが「ラピュタは何度でも甦る。それが人類の夢だからだ」と主張するのに対して、シータは「自分にはラピュタが滅んだ理由がよく分かる。人は、土を離れては生きられない」と主張します。この作品が描かれてから40年あまり、作品が訴えかけるメッセージは、いまを生きる私たちにはどのような響きを持って受け止められるでしょうか。
ちなみに、筆者は本論の最後を次のように締めくくりました。
そしてこうした現生人類の八方塞がりに頭を悩ませるとき、筆者はふと思うことがある。ネアンデルタール人は、4万年前まで現生人類と共存し、火を使い、集団で狩りを行い、装飾品さえ製作していた。つまり私たちとは別種の存在でありながら、「社会環境」を膨張/蓄積させるサイクルを独自に持っていたのである。もしも彼らが絶滅することなく、いまでも生き延びていたとするなら、はたして彼らはどのような世界を築きあげたのだろうか――と。
上柿崇英(2025a)「「天空城」はどこへ?――環境問題の起源と「社会環境」の人類史」p.108 より
「天空城」はどこへ?――それは自然生態系=「自然環境」のうえに人工的な環境=「社会環境」をつくりだし、しかもそれを、世代を越えて膨張/蓄積させていくという特殊な性質を備えた存在であるところの、私たち人類の運命、そして未来についての問いにほかならないのです。
※noteの方からも全文を読むことができますので、詳しくはそちらもご参照ください。
「天空城」はどこへ?――環境問題の起源と「社会環境」の人類史行方
はじめに
1.そもそも環境とはなにか?
(1)生物存在から考える、主体と環境の関係性
(2)環境を創造する生物としての人間存在
(3)人工的な環境としての「社会環境」の構造
2.人類史から見る「社会環境」の変遷史
(1)「社会環境」はいつ成立したのか?
(2)農耕社会の成立が意味したこと
(3)化石燃料社会の成立が意味したこと
(4)「定常状態」から環境問題を考える
3.「天空城」の比喩
(1)環境問題とは何であったのか
(2)「天空城」としての人間社会
(3)「天空城」に与えられた選択肢①――「天空城」の帰還を考える
(4)「天空城」に与えられた選択肢②――「天空城」の浮上策を考える
(5)「天空城」に与えられた選択肢③――「天空城」の要塞化と、惑星の「天空城」化
おわりに――「天空城」はどこへ?
以下、冒頭の部分について転載しておきます。
人間が環境を改変し、その結果として環境問題が生じていることはよく知られている。しかしそもそも環境を改変するとは何を意味するのか、またそうした行為を行う人間とはいかなる存在なのか?――ここまで考えている人々は少ないかもしれない。
例えば想像してみて欲しい。ビーバーが河をせき止めてダムを造り、シャカイハタオリが草木を編んでマンションを建てるように、環境を改変するのは決して人間だけではない。
またいかなる生物も、何かが引き金となって、ときに生態系のバランスを攪乱させてしまうことがある。要するに、環境を破壊するのは人間だけではないのである。
それにもかかわらず、人間が行う環境の改変や、人間に由来する生態系の攪乱には、やはり他の生物種が行うものとは異なる側面があるように見える。問題は、その違いとは何かである。
人間には、人工的な環境それ自体を創出し、しかもそれを次世代へと脈々と継承していく特殊な能力が備わっている。実は今日私たちが環境問題と呼んでいる事態には、この人間固有の性質が深く関わっているのである。
では人間とは、そもそも環境破壊的な生き物であり、気候変動を含む今日の事態は、そうした人間存在による必然的な結果だということになるのだろうか。そうとも言い切れない。なぜなら、700万年の人類の歩みから見えてくるのは、人間と環境をめぐる関係性の劇的な変容であり、それに伴って私たち自身の姿もまた変容を遂げていくドラマだからである。
本論では、この環境を改変する人間とはいかなる存在なのかという問いから出発し、700万年に及ぶ人類の歩みから環境問題の起源について考える。とりわけホモ・サピエンスが現れ、農耕社会が成立し、化石燃料社会が成立してきたことの意味を、人間と環境の関係性の文脈から読み解き、そのうえで現在の私たちが置かれた状況について、「天空城」の比喩を用いて環境哲学的に考えてみたい(※1)。
人類が創出した人工的な「社会環境」は、「自然環境」から分離し、肥大化し、やがて化石燃料を動力とした自己完結型のシステムへと変貌した。それはあたかも「自然環境」から浮遊した「天空城」のごときものであり、私たちに問われているのは、まさしくこの「天空城」をどこへ導いていくのかという問題だからである。
はたして私たちは、この自己完結した巨大なシステムを再び大地に根づかせようとするのだろうか? それとも何とかしてそのシステムの浮遊状態を持続させようと奮闘し続けるのだろうか? ――そのことが問われているのである。
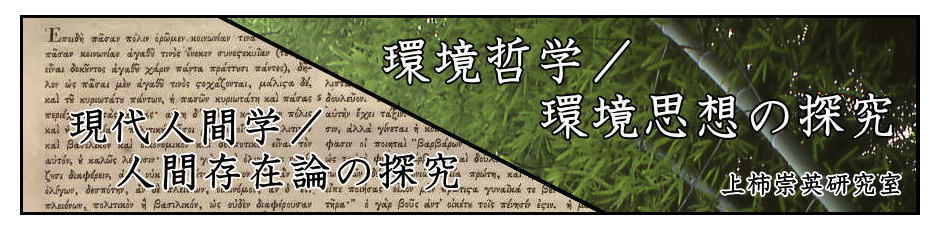
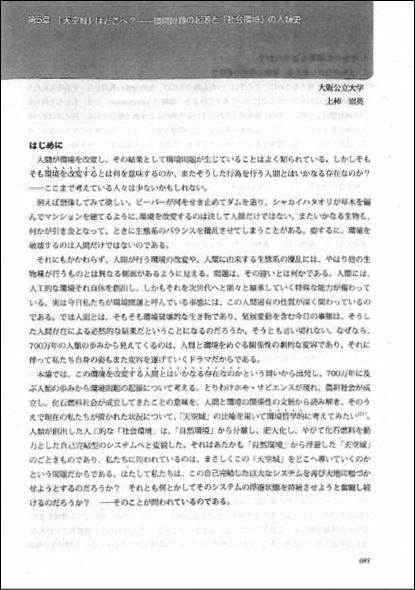
-1024x536.jpg)