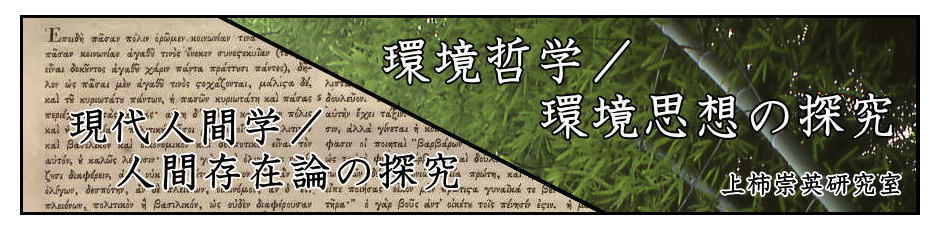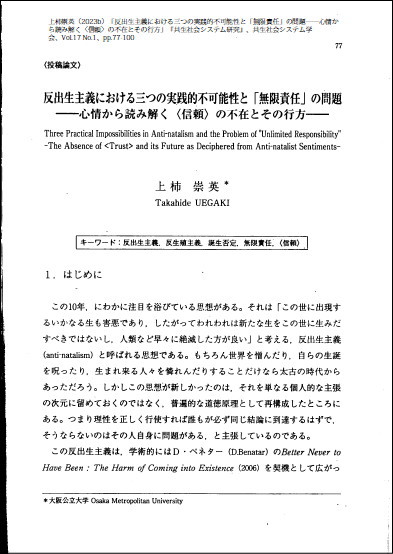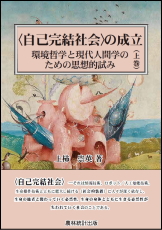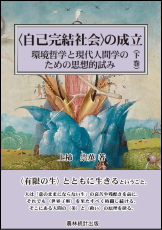反出生主義について1年前に執筆した原稿がようやく刊行されました。
反出生主義とは、「この世に出現するいかなる生も害悪であり、したがってわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではないし、人類など早々に絶滅した方が良い」という主張を普遍的な道徳原理として掲げる思想で、ベネターの『Better Never to Have Been : The Harm of Coming into Existence』(2006)を通じて世界的に知られるようになりました。
本論もベネターについては触れていますが、切り口はかなりユニークではないかと思っています。反出生主義について書かれた論考の多くは、反出生主義の理論的枠組みの正誤に焦点が当たりますが、本論の場合そうではなく、人々がなぜ反出生主義に惹かれるのかという心情の方に力点をあてているからです。
(追記:また、先行きの不透明さや格差といった経済問題に絡めて論じる方もいますが、本論はそのアプローチとも異なります。詳しくは注の22を参照)
今回の論考を通じて、「無限責任」という概念に行きつくことができました。これは本来一人の人間が背負えるはずのない責任を、それでも一人で負わねばならないと思ってしまう現代人が抱える強迫観念のことです。
私たちは、生きている限り、誰かに影響を与えずにすむことも、また自分の人生の全責任など背負いきれるはずもないのに、誰も苦しめず、誰も傷つけず、誰にも迷惑をかけまいとして焦燥してしまっています。未来を正確に予測することも、未来を意のままにできることもないはずなのに、生まれ来る誰かの人生の全責任をたった一人で背負わなければならないと感じてしまっているわけです。
本論が主張するのは、この「無限責任」という歪な世界観=人間観こそが、実は人々を反出生主義へと誘う結果となっているのではないかということです。つまり「無限責任」が要求する、そもそも実現不可能な“あるべき人間”の理想に駆り立てられ、「そんな責任など背負えるはずがない」、「そんな人間が新たな命など生みだす資格はない」と追いつめられた人々が、「この世に出現するいかなる生も害悪であり、そもそもわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではない」と聞いて、どこか救われた気がしてしまう。そうした私たちの世界観=人間観に潜む病理こそが、真に問題にされるべきではないのか、ということです。
本論では、
「反出生主義者は、決して無責任な人々なのではない。おそらく誰よりも責任を感じるからこそ、そして真面目に生きようとするからこそ、人々はかえって反出生主義者になる。世界や人間を心底憎んでいるから、人々は反出生主義者になるのではない。おそらく誰よりも世界や人間を祝福したいと願い、その高すぎる理想に屈折したからこそ、人々は反出生主義者になるのである。」(上柿 2023b: 92-93)
「したがってわれわれの社会が、この先も互いの生の責任を分け合おうとすることなく、〈信頼〉を育くむことを怠り、ありもしない自立の幻想に浸り続けるのだとしたら、人々はますます反出生主義者に転向せざるをえないだろう。」(上柿 2023b: 93)
と書きました。しかしここでの〈信頼〉については、実は、迷いもあるのです。私に反出生主義を考えるきっかけを与えてくれたある方が言ってくださったように、「そのような〈信頼〉など、人類は一度として手にしたことなどなかったのではないか」と、私も心のどこかで、ふと思うことがあるからです。私もまた、「無限責任」に苦しむ現代人の一人なのかもしれません。
反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題――心情から読み解く〈信頼〉の不在とその行方
1.はじめに
1)反出生主義の定義について
2)ベネターの反出生主義と非対称性の問題
3)反出生主義への反論や誤解
2.反出生主義の実践的不可能性
1)「苦痛除去の不可能性」という問題
2)「選択の不可能性」という問題
3.反出生主義の背景にあるもの
1)「反出生主義的心情」の所在
2)「無限責任」の牢獄と「自立の不可能性」という問題
3)〈信頼〉なき世界のゆくえ
4.おわりに
以下、冒頭の部分について転載しておきます。
反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題――心情から読み解く〈信頼〉の不在とその行方
この10年,にわかに注目を浴びている思想がある。それは「この世に出現するいかなる生も害悪であり,したがってわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではないし,人類など早々に絶滅した方が良い」と考える,反出生主義(anti-natalism)と呼ばれる思想である。もちろん世界を憎んだり,自らの生誕を呪ったり,生まれ来る人々を憐れんだりすることだけなら太古の時代からあっただろう。しかしこの思想が新しかったのは,それを単なる個人的な主張の次元に留めておくのではなく,普遍的な道徳原理として再構成したところにある。つまり理性を正しく行使すれば誰もが必ず同じ結論に到達するはずで,そうならないのはその人自身に問題がある,と主張しているのである。
この反出生主義は,学術的にはD・ベネター(D. Benatar)のBetter Never to Have Been : The Harm of Coming into Existence(2006)を契機として広がっていった(1)。しかし本論が注目したいのは,それが学術界を超えて少なくない人々の共感を密かに呼んでいることである。それはなぜなのだろうか。その背景にあるものとは何なのだろうか。このことを考察するのが本論の目的である。
本論では,まずベネターが提示した反出生主義の基本的な枠組みについて確認し,その問題点について考える。その際特に着目したいのは,この思想を現実に落とし込むことによって生じる不可能性の数々である。反出生主義の枠組みは,思考実験としては成功しているものの,それは純粋に理念の世界の産物でしかない。本論では,このことを「苦痛除去の不可能性」,「選択の不可能性」,「自立の不可能性」という三つの実践的不可能性の観点から独自に分析し,この思想がいかに人間的現実と乖離した前提から構築されているのかということについて見ていこう。
だが本論にとって重要なことは,それでも少なくない人々がこの思想に惹かれてしまう根源的な理由である。本論では,反出生主義に共鳴する人々の心情に着目することによって,その背景に,自身のあらゆる行動の全責任を無制限に負うべきだとする「無限責任」の思考が潜んでいることを指摘したい。反出生主義者は自身が意図せずして誰かを不幸にしてしまうことを恐れているのであり,自身の身勝手な理由から,将来不幸になるかもしれない何ものかを生みだすことが許されるのかと苦しんでいる。だが,考えてもみてほしい。そのような責任など,そもそも一人の人間が背負えるようなものだったのだろうか。問うべきことは,そもそも現実的には想定しがたいはずの責任を,それでも負うべきだと感じてしまう,われわれの歪んだ「世界観=人間観」なのである。
本論では,こうした「無限責任」という名の幻想が,歴史的にはつい最近になって現れたものに過ぎないことについて確認する。そしてわれわれの社会においては,実際に互いの生の責任を分け合うための〈信頼〉が欠落していることに目を向けたい。もしもわれわれが,これからも社会全体として〈信頼〉を育むことができず,ありもしない自立の幻想に浸り続けるのだとしたら,人々は「救い」を求めて,ますます反出生主義に傾倒せざるをえないだろう。