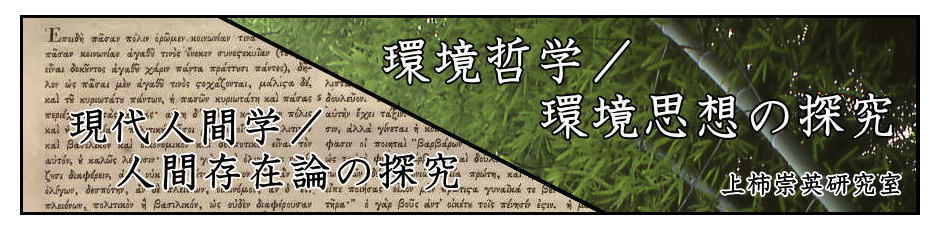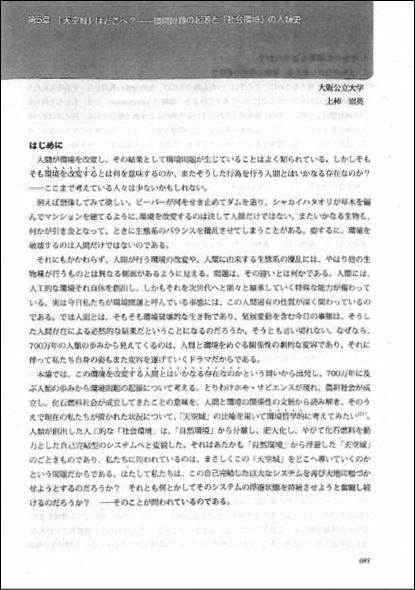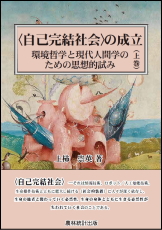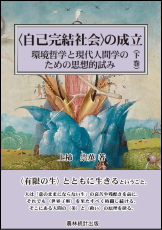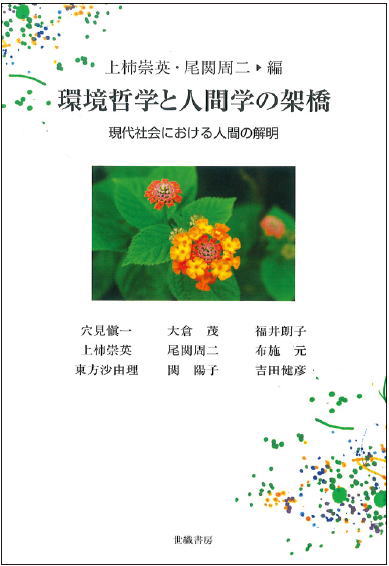所属している学会との関連で「ポスト・ヒューマン」の用語説明を頼まれたのですが、記事が長くなったので分割することになりました。せっかくですので、分割前の文章をnoteに掲載しました。
「ポスト・ヒューマン」とは何か?
はじめに
・「実体としての人間」の揺らぎ
・「準拠点としての人間」の揺らぎ
・ポストヒューマニズム
・トランス・ヒューマニズム
おわりに
ポストヒューマン(post-human)とは、直訳すると「人間以後」となりますが、この概念が注目されているのは、近年のAIやロボットや生命操作技術などの進展によって、これまで私たちが「人間」という形で想定してきた枠組みが急速に解体しつつあることが関係しています。
そうした時代状況を反映する形で、また人間を捉える新たな枠組みを問題にする際に、ポストヒューマンという概念が用いられているのです。
もっとも、ポストヒューマンという語をめぐっては、論者によっていくつかのニュアンスが錯綜している部分があります。そのため本論では、そのあたりを整理することを目指して、ふたつの軸を導入することにしました。
第一の軸は、現象/社会的現実としてのポストヒューマンに着目したもので、私たちがポストヒューマンという際に、それがいかなる意味において「人間以後」なのかをめぐって設定されたものです。
そこでは一方で、生物学的な「ヒト」を含め私たちが「実体としての人間」だと見なしてきた枠組みが揺らぐという意味で「人間以後」と見なす場合と、他方では、人間こそが物事の価値や基準の中心にあるとする「準拠点としての人間」という前提が揺らぐという意味で「人間以後」と見なす場合とがあり、両者を区別することができます。
ここでは、遺伝子治療、エンハンスメント、BMI、メタバース、アバターなどを前者=「実体としての人間」の揺らぎをめぐる問題として、家族となるAI/ロボット、管理や判断を行うAI、汎用人工知能(AGI)、動物の権利などを後者=「準拠点としての人間」の揺らぎをめぐる問題として扱っていますが、重要なのは着眼点の違いですので、具体的な事例を入れ替えて論じることもできるでしょう。
次に第二の軸は、ポストヒューマンを現象/社会的現実として捉えるというよりも、思想的にどのように位置づけるているのかという点に着目したものです。特に私たち自身がポストヒューマンな存在になること、あるいは世界がポストヒューマンなものとなっていくことに対して、積極的な意味を付与するかどうかをめぐって設定されます。
このとき、私たちがポストヒューマンな存在になることに積極的な意味を見いだすグループが、トランスヒューマニズムです。例えばシンギュラリティで有名なカーツワイルや、2023年頃にChatGPTをめぐって論陣を張った効果的加速主義(e/acc)などは、ここに位置づけられます。
他方でポストヒューマンをめぐる多くの議論は、私たちがポストヒューマンな存在になることを必ずしも推進しているわけではありません。そこで本論では、ポストヒューマンに関する思想的な言説一般のことを、トランスヒューマニズムと区別する形で、ポストヒューマニズムと定義します。
ただしポストヒューマニズムという言葉には注意が必要です。というのも、これを「ポストヒューマン・イズム」と理解するか、「ポスト・ヒューマニズム」と理解するかでニュアンスが大きく変わってくるからです。
例えばハラリが『ホモ・デウス』で論じた無用者階級論、あるいは人間の絶滅以後の世界を思想的に論じた場合などは、ポストヒューマンについて論じた言説ではあるものの、それを推進しているわけではないので、ポストヒューマニズム(ポストヒューマン・イズム)の事例として位置づけられます。
他方でポストヒューマニズムを「ポスト・ヒューマニズム」と理解する場合には、特別な意味が付与されることになります。端的に言うと、カントに代表される「道徳的で理性的な主体」としての人間を批判する思想/言説というニュアンスです。
こうした意味での「人間の終焉」を哲学的に提示したのはフーコーですが、その系譜から、例えば”主体”そのものを否定したり、人間以外の「何ものか」を”主体”と見なす場合など、「近代的な主体=人間中心主義(ヒューマニズム)」を批判する思想的立場は、この文脈ではすべてポストヒューマニズム(ポスト・ヒューマニズム)として位置づけられます。具体的には、フェミニズムからロボット/AIの権利論、動物の権利論、アクターネットワーク論などがこれにあたります。
さて、以上が本論の概要なのですが、本論を整理するにあたって改めて感じたことがあります。それは、ポストヒューマンを論じた多くの文献が、上記の整理で言うところの「ポスト・ヒューマニズム」から議論を行っていること、その結果ポストヒューマンが「準拠点としての人間」の揺らぎという視点に偏る形で論じられているように感じるということです。
なかでも多いのは、フェミニズムの文脈でポストヒューマンを論じたブライドッティの枠組みを出発点とする議論ですが、こうなると、ポストヒューマン論とは「近代的主体なきあとの主体をめぐる問題」となってしまい、議論の射程が大きく狭まってしまいます。
筆者の考えでは、ポストヒューマンという概念が注目されている最大の理由は、私たちの現実的な問題として、これまで自明視されてきた生物としての「ヒト」の枠組みが解体していっていること、またそれを是が非でも推進すべきだと論陣を張る人々が実際に存在する――しかもそれなりに大きな影響力を持つ形で――ことにあります。
つまり、時代が要請しているのは、むしろ「実体としての人間」が揺らぐという現実をどう考えるのか、またトランスヒューマニズムとどのように向き合っていくのかという問題であるということです。
もちろん「主体」を考察することで見えてくることはたくさんあります。実際私たちは、「人間ならざる何ものか」に注目することによって、これまでの常識的なものの見方が揺らぎ、これまで自明視してきた世界の姿が違って見えることになるでしょう。そしてその過程で、聞こえていなかった声や、見えていなかった抑圧の姿を見聞きすることになるかもしれません。
しかしそれはあくまで「目なざし」の問題です。ポストヒューマン時代に問われているのは、より現実的な問題だからです。例えば次の問いについて、皆さんならどのように考えるでしょうか?
――もしもある状況において、AIが人間よりも正確な判断を下せるとしたら、私たちはそれに従うべきだろうか? もしもAIが人間よりも効率的に組織を管理できるとするなら、私たちはそれをAIに任せてしまった方が良いのではないか?
――もしも創造性を含めて、あらゆる能力においてAIが人間と同等か、あるいは人間以上だとするなら、なお人間が存在する価値はどこにあるのだろうか?
――もしもAIやロボットが人々にとって理想の友人や恋人や家族になってくれるのだとしたら、人間はなお、意のままにならない生身の他者と関わっていくことに意味を見いだしうるのだろうか?
――もしも高度に発達したメタバースを通じて、「なりたい私」=アバターとして充実した生が成立するとき、私たちはなお、望んだわけでもないこの身体に特別な意味を見いだしうるのだろうか?
――もしも精巧で十分に美味しい人工肉が手頃に入手できるとして、それでもなお私たちは、敢えて生身の動物を殺害することに正当性を見いだしうるのだろうか?
つまりポストヒューマン論にとって重要なのは、ただ「主体」を論じることではなくて、その先にあるもの、つまり現実として現れるだろうポストヒューマンな存在、あるいはポストヒューマンな世界に対して、いかなる意味を与えることができるのかまでを論じることだ思うのです。
私たちが望むと望まざるとに関わらず、私たちはポストヒューマン化が加速していく時代を生きています。そしてそれを避けることはおそらくできないでしょう。そのことを引き受けたうえで、なおそこで現れる新しい〈人間〉とはいかなる存在なのか? そして翻って私たちは結局「何もの」だったのか? そのことがいま、改めて問われているのだと思うのです。